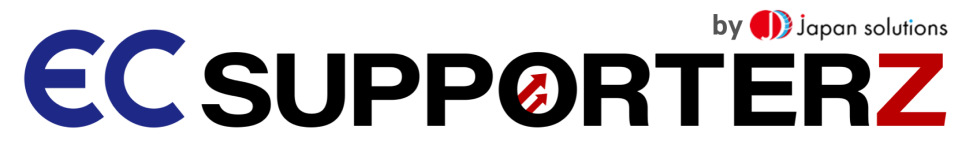楽天市場の競合店舗の売上はいくら?概算方法と競合に勝つ戦略
楽天市場には56,000件程度の店舗が出店しており、なかには同業他社とも呼べる店舗が存在しています。
ユーザー数は5,000万人以上といわれており、日々増加傾向にありますが、ほとんどの場合ユーザーの取り合いになります。
限られた分母のなかから自店舗で購入してもらうユーザーを獲得するためには、他店舗との差別化を図らなければなりません。
こちらの記事では、楽天市場の競合店舗はいくら売り上げているのかについて、概算方法や勝ち方について解説します。
そもそも楽天市場における競合とは?

一般的に「競合」という言葉は、自分の成果を妨害する、自分の成果を達成する際に障害となる存在を指します。
楽天市場においても同様であり、自店舗の売り上げをおびやかしたり、ユーザーを奪ったりするような店舗が競合になります。
しかし、楽天市場に出店している56,000件程度の店舗すべてが、自店舗を利用するユーザーを奪おうとはしていません。
楽天市場における自店舗の競合は、下記のように「自店舗で売れているものを取り扱っている店舗」と「自店舗の取扱商品と類似する商品を取り扱っている店舗」になります。
自店舗で売れているものを取り扱っている店舗
楽天市場に出店している多くの店舗では、特に売れ行きが良い商品を取り扱っているところがあります。
価格メリットが大きい、持ち運びが不便な商品などが売れている商品に含まれます。
これらは店舗によって異なりますが、場合によっては同じ商品を複数の店舗が販売していることがあります。
その結果、ユーザーは価格や配送日数などを考慮して店舗を選定することになるため、店舗同士の競争が発生します。
「最近、○○の売れ行きが悪い」と思ったときは、競合店舗にユーザーを取られている可能性があります。
そのような場合、対象となる商品を検索し、上位表示されている店舗を見てみましょう。
対象となる商品が多岐にわたる場合は、上位10店舗や上位表示されている店舗が競合となります。
自店舗の取扱商品と類似する商品を取り扱っている店舗
「○○専門店」といえる店舗は楽天市場内に多数出店しており、こちらは直接的な競合店舗となります。
ショッピングモールでいうと、自店舗の横に同じ商品を取り扱っている店舗が出店している、ということと言い換えられます。
また、メーカーが違っても同じような商品というものは市場に多く流通していることから、ユーザーの比較対象になります。
自店舗で販売している商品を他店舗が販売しているだけでは、大きな競争要因となりません。
その商品の販売価格が低かったり、そのほかに豊富な商品が取りそろえていたりすると、脅威となります。
類似した商品を取り扱っていると考えているのは競合店舗も同様であり、何らかの手段で差別化を図って競争優位に立とうとします。
そのため、自店舗の取扱商品と類似する商品を取り扱っている店舗を発見した場合、自店舗の独自性を構築する必要があります。
競合分析の考え方

こちらでは、競合分析の考え方についてご説明します。
自店舗の理解を深める
競合店舗を分析し、差別化戦略を実践するためには、自店舗の理解を深める必要があります。
どの商品がどれだけ売れており、直近数ヶ月の売り上げの推移など、まずは現状の把握が重要です。
分析を進めていくうちに、「○○が売れていない」「意外と○○が売れている」といった気付きを得られるでしょう。
また、性別や年齢といったユーザー像も理解しておくことで、プロモーション方法やページデザインの参考にもなります。
販売している各商品が検索キーワードにおける占有率や、広告の表示枠なども重要な情報です。
キーワードが上位表示されていない場合はSEO対策を行い、広告の表示枠に入っていない場合は運用方針を見直します。
このように、自社の理解を深めるだけでも、さまざまな改善案を立案することができるのです。
楽天市場を利用するユーザーの特性を理解する
楽天市場を利用するユーザーは、大きく分けて下記の2種類があると考えられています。
- 明確に欲しい商品があるユーザー
- 隙間時間など、ネットサーフィンを楽しんでいるユーザー
前者の場合は購入予定の商品が決まっているため、指名検索で商品を探す傾向にあります。
一方、後者の場合は「良い商品がないかな」と、とりあえず検索をしてみるユーザーを指します。
「Tシャツ 赤」や、もっとざっくりと「アウター」といった、指名検索以外の検索ワードを使用する人がいます。
これらのユーザーが購入する際、下記の要素を考慮して購入する店舗を決定します。
- 商品のサムネイル
- 楽天ポイント還元率
- 商品レビュー数
- 送料負担
- 配達タイミング
そのため、店舗運営者はどのようなユーザーをターゲットにし、自店舗で購入するメリットを明確にする必要があります。
競合他店舗との違いを明確にする
自店舗や楽天市場を利用するユーザーの違いを理解したあとは、競合他社との違いや差別化要因を検討します。
まずはベンチマークとなる競合他社を、2から3店舗ほどピックアップしましょう。
条件は「自店舗で売れているものを取り扱っている店舗」や、「自店舗の取扱商品と類似する商品を取り扱っている店舗」になります。
これらの条件に該当する競合他店舗を決めたら、商品ページを参照してページ構成や価格、送料の有無などの条件を書き出します。
書き出した条件を自店舗の条件と照らし合わせることで、何が強くて何が弱いのかを知ることができます。
自店舗の弱みについてはすぐに解決できるものもありますが、経営に関わるなど解決に時間がかかるものなどがあります。
そのため、競合他店舗の理解を深め、課題を抽出したあとは、課題解決の優先順位を決めておきましょう。
自然検索とRPP広告の露出・流入状況を可視化する
楽天市場における主なプロモーションとして、自然検索を強化する「SEO対策」と、費用を支払って露出を増やす「RPP(Rakuten Pop-up Page)広告」があります。
SEO対策はキーワードで上位表示を目指す施策であり、上位表示されるほど多くのユーザーの目にとまり、流入量が増加します。
広告については一定の費用は発生しますが、配信後すぐにユーザーに表示されるといった特徴があります。
SEO対策はすぐに成果が現れるわけではありませんが、上位表示を獲得し続けることで継続して成果を得ることができます。
これらの施策は実施して完了ではなく、施策後に分析を行って成功・失敗を確認することが重要です。
なぜ成功したのか、なぜ失敗したのかを検討し、考えられる要因を特定することでほかのページに活かすことができます。
すべてのページを施策すると多くの時間を要してしまうため、まずは売りたい・売れている商品から始めるのをおすすめします。
顧客ニーズを理解し、RPP占有率を最適化する
楽天広告(RPP広告)の占有率とは、対象となる広告枠でどれくらい占有していたかを表す数値です。
RPPは有料の広告であり、露出状況は予算や入札単価などの戦略に大きく依存します。
たとえば、自店舗のRPP広告予算が他店舗よりも低かった場合、表示されないため占有率が下がってしまいます。
とはいえ、予算をかけるほど費用対効果が下がってしまうため、損益分岐点の調査が重要です。
ほかにも、特定のキーワードで検索ボリュームが大きい場合、そのキーワードの入札額を高めることで改善が可能です。
ユーザーが価値を感じると考えられる商品特性を強調することでも、クリック率と占有率を高めることができます。
そのためには自店舗で検索されているキーワードや、競合他店舗で出稿しているであろうキーワードの調査が必要になります。
競合分析を実施するメリット

下記は、競合分析を実施することで得られるメリットになります。
市場の理解
競合分析を実施する際、対象となる商品の需要やユーザー動向について検討するため、市場を理解することができます。
キーワードの検索状況や広告の配信状況なども含まれており、ボリュームが大きいキーワードほど高い需要があるといえます。
また、分析の際には楽天内だけではなく、経済やメーカーの状況などを参考にすることがあります。
仕入れ先の情報を競合店舗よりも早く得ることで、楽天市場内のページなどに反映させることができます。
情報は見えない資産ですが、店舗の売り上げに大きく影響を及ぼし、差別化要因となるのです。
このように、市場を理解することでビジネス戦略やマーケティング戦略など、さまざまな施策に活かすことができます。
競合の理解
競合分析である以上、競合他社に関する理解が深まるのは当然と考える人がいるかもしれません。
しかし、しっかりと分析を行うことで、これまで見えていなかった情報が可視化され、対策を打ちやすくなるのです。
たとえば、これまでは検索結果に表示されているという認識だった競合のページを見てみることが挙げられます。
検索結果にはサムネイルや価格、送料、付与されるポイント、カラーバリエーションなど、さまざまな情報が表示されます。
これらを確認するだけでも対策は可能ですが、価格については一時的な対策となってしまう可能性が高いです。
競合他店舗も値下げをすることで永遠に価格競争が発生してしまい、結果として赤字ギリギリの経営となるでしょう。
ページ内を確認することで、構成や写真の見せ方、説明文、注力キーワードなど、さまざまな情報を得ることができます。
自店舗の理解が深まる
楽天市場で競合他店舗に関する情報を収集する理由は、自店舗との差別化要因を明確化することが挙げられます。
そのため、おのずと自店舗に関する理解を深められる点も、競合店舗分析によって得られるメリットといえます。
楽天市場を運営していると、受発注管理や梱包、発送といったさまざまな業務を毎日実施しなければなりません。
なかなかひと段落つけず、就労時間後も翌日の業務負担を減らすために作業をしている人もいることでしょう。
分析に関する時間を取りにくいことから、意外と自店舗に関する情報を得ていない店舗は多いものです。
とはいえ、現状や競合店舗の状況などを分析しなければ売り上げを伸ばしにくいため、定期的に時間をかけることをおすすめします。
分析に時間をかけた結果、競合店舗だけではなく自店舗に関する理解を深められる点も競合分析で得られるメリットといえます。
戦略立案時の判断材料になる
自店舗や競合店舗の売り上げを知ることで、市場や楽天市場内における自店舗のポジショニングが明確になります。
競合店舗が〇千万円程度の売り上げが予測され、自店舗がそれ以下だった場合、改善の余地があるといえます。
楽天市場で売り上げを上げるためには、客単価を上げる・転換率の改善・ユーザー数を増やすなどが挙げられます。
上記のうち、施策の難易度や成果比較がしやすいことから、ユーザー数を増やす店舗が多い傾向にあります。
まずは多くのユーザーを集客し、その後客単価や転換率を改善することで、現状よりも高い成果を得られるでしょう。
また、競合店舗が特定のセグメントでシェアを獲得している場合、そのセグメントを避ける、といった戦略も実施できます。
さまざまな戦略を立案できる判断材料を集められる点は、競合分析のメリットといえるでしょう。
リスク管理能力が向上する
安定した売り上げを継続して得られたとしても、ある日突然売り上げが下がってしまった、という状況におちいることがあります。
「もっと販売しなければ…」と考えて運営しても、なかなか状況が回復しないこともあるでしょう。
そのような場合は自店舗、および競合店舗を分析し、現状を理解したうえで対策を検討しなければなりません。
ビジネスにおいて「知っている」と「知らない」では大きな差があり、知らないでは済まされないことがあります。
知らないことを知ったうえでさまざまな施策を検討することで、現状や今後発生するリスクに対応できるのです。
また、良く調べてみるとチャンスとなるセグメントを発見できることから、分析も立派な運営業務といえます。
そのため、店舗運営者は定期的に自店舗・他店舗・市場について調べることをおすすめします。
競合の調査方法
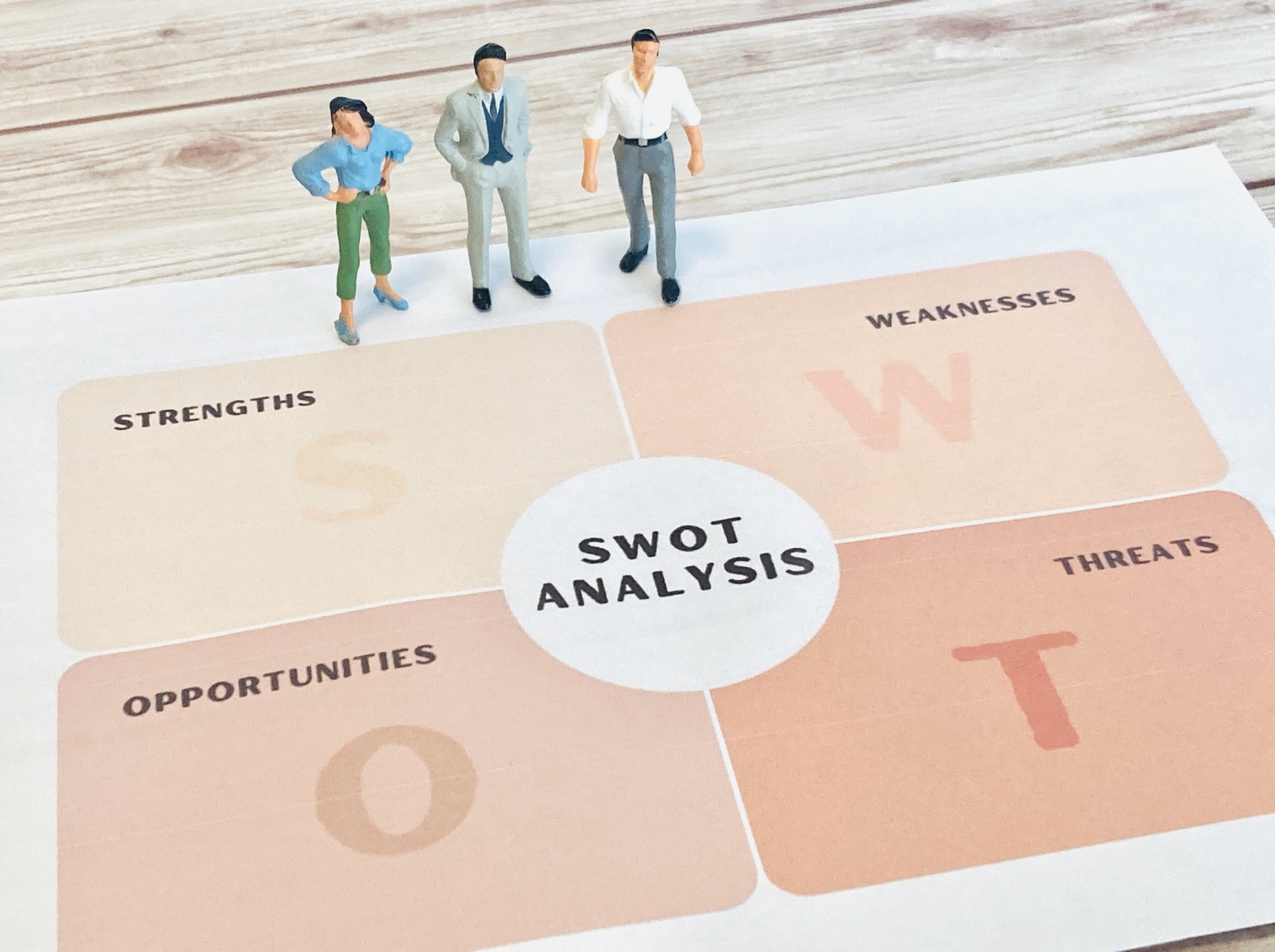
一般的に、競合を調査する際は下記の「3C分析」「SWOT分析」「4P分析」「コホート分析」が用いられます。
こちらでは、それぞれについてご説明します。
3C分析
3C分析は顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの要素を分析する調査方法になります。
先述したユーザーと競合店舗、自店舗がこれらに該当する要因であり、それぞれを調べることで特性を理解できます。
ユーザーでは購買行動や性別・年齢といった属性を調査します。
競合店舗については商品ラインアップや価格設定、マーケティング戦略などを調べます。
最後に自店舗については、先ほど調べたユーザーや競合店舗情報と比較して、情報を照らし合わせます。
さまざまな情報と自店舗を照らし合わせることで、自店舗に足りない要素や強みなどを理解することができます。
とはいえ、3C分析はもれなく・ダブりなく「MECE」を満たせるわけではなく、分析に時間がかかるデメリットがあります。
多くの時間が必要だと感じたときは、ほかの方法で分析するか大枠だけをつかむようにしましょう。
SWOT分析
SWOT分析は強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)の4つの要素で自店舗・競合店舗を評価する方法です。
一般的には左に弱み、右に強み、上に機会、下に脅威でセグメントを十字に切って図にして用いられます。
たとえば、同じ商品を取り扱っていて価格メリットがある場合は、強みかつ驚異の欄に記載します。
一方、同じ商品を取り扱っていて、納期が自店舗のほうが短い場合は強みかつ機会の欄に記載することになります。
SWOT分析を用いることで、市場の変化や新たな顧客ニーズなどを理解することができます。
一方、SWOT分析にはグレーゾーンがなく、主観的な判断におちいりやすいといったデメリットが存在します。
とはいえ、これらについては施策を実施してから再度検討することで、調整が可能となります。
4P分析
4P分析は商品(Product)、価格(Price)、プロモーション(Promotion)、販売場所(Place)の4つの要素で分析する方法です。
競合が類似商品を取り扱っている場合、商品同士を比較する際に用いられます。
先述したSWOT分析のように、強みや弱みを明記することで、自店舗が取り扱う商品の特性を理解することができます。
商品に対する具体的なマーケティング戦略を立案でき、施策をスムーズに実行できる点がメリットといえます。
また、実施した施策の成否や改善がしやすい点もメリットといえるでしょう。
一方、主観に依存し、総合的な視点が薄れてしまうほか、商品が多くなるほど分析にかかる時間が必要になります。
このことから、4P分析の注意点は「木を見て森を見ない」状況におちいらないようにすることが挙げられます。
コホート分析
コホート分析は、特定の期間や条件でグループ化された顧客の行動パターンを分析する手法になります。
たとえば、キャンペーンごとに設定した「コホート」の、月ごとの転換率や客単価の変化を分析することが挙げられます。
これらの変化より、ユーザーニーズや市場のトレンドなどを把握することができます。
どちらかというと長期的な施策を評価する際に用いられる分析方法であり、一定期間運用しなければならない点には注意が必要です。
とはいえ、トレンドを知ることができたり、ユーザーニーズを把握できたりする点はメリットといえるでしょう。
これらの情報を得ることで、どの商品をいくら在庫しておくべきといった需要予測に活かすことができます。
楽天市場ではスーパーセールやお買い物マラソンなどさまざまなキャンペーンがあるため、それぞれで分析すると良いでしょう。
競合の売り上げ規模の調査方法

では、実際に競合店舗がいくら売り上げているのかを知る方法はないのでしょうか?
結論として、競合店舗の具体的な売り上げを知る方法はありませんが、およその数値を予測方法なら存在します。
下記は競合店舗の「おおよその」売上金額を調べる方法になります。
競合店舗の売り上げランキングから考える
通常、楽天市場の売り上げランキングは特定の期間内に売り上げが高い順に並べられています。
特定の商品単体で売り上げを上げたい場合、競合店舗の売り上げランキングかラ概算することができます。
たとえば、商品Aについて自店舗が1ヶ月間に10個販売しており、ランキングが3位だった場合を考えます。
競合店舗が1位だった場合、楽天の売り上げランキングから最低でも12個以上は売れていると推測できます。
単価は楽天市場のページに表示されていることから、商品単体の売り上げは「単価 × 売れたであろう個数」で算出します。
一方、売り上げランキングはあくまで相対的な情報であることから、正確な数値を示すものではない点には注意が必要です。
とはいえ、売り上げランキングで上位を獲得するためにはいくつ以上販売すれば良いという指標を得られる点は、メリットといえます。
レビューから人気度を考える
レビューには購入したユーザーの体験談や感想が記載されており、これらを確認することでおおよその売り上げを知ることができます。
たとえば、使った感想が10件、体験談が15件だった場合、最低でも25個は購入されていると考えられます。
しかし、購入してもレビューを記載しないユーザーもいるため、あくまで概算になります。
それでも、「この店舗は○○を、最低○個販売している」という情報は、大きなアドバンテージとなるのではないでしょうか。
対象となる商品ページを確認・分析し、自店舗にも取り入れることで、競争優位に立つことができるでしょう。
ほかにも、調査したいジャンルやキーワード、検索上位の商品、レビューが多い商品などを参照することで、売り上げの概算が可能です。
市場調査や業界データを利用する
楽天市場は日本最大級のECプラットフォームであり、さまざまなカテゴリに属するアイテムを販売しています。
楽天市場全体の売り上げや業界のトレンドを把握することで、競合店舗の売り上げを概算することができます。
下記、市場調査や業界データを利用して競合店舗の売り上げを概算する手順になります。
- 楽天市場に関する市場調査レポートや、業界レポートを収集する
- 市場全体における売り上げ推移や成長率を調べる
- 主要なプレイヤー販売店を調査する
たとえば、去年の市場規模が1,000億円、成長率が2%の場合、今年の市場規模は単純計算で1,020億円になります。
市場調査レポートや業界レポートに「昨年と同様の推移」と記載されていれば、上記数値のまま検討できます。
主要なプレイヤーに競合店舗が含まれており、販売シェア率が記載されていた場合はそちらを参照しましょう。
競合店舗の販売シェア率が全体の5%だった場合、1,020億円 × 5% = 51億円になります。
先述のとおり、これらの調査方法はあくまで概算であることから、過信せず、参考程度にとどめましょう。
それでも、大まかでも目標値や指標を知れるという点では、大きな情報だといえるのではないでしょうか?
まとめ|競合を知ることで自店舗の理解も深まる

こちらの記事では、競合店舗がいくら売り上げているのかを知る方法について解説しました。
楽天市場における自店舗の競合は、「自店舗で売れているものを取り扱っている店舗」と「自店舗の取扱商品と類似する商品を取り扱っている店舗」になります。
自店舗で売れているものを取り扱っている店舗は、価格や配達日数などで差別化を図っていることがあります。
自店舗の取扱商品と類似する商品を取り扱っている店舗は価格や配達日数のほか、商品ラインアップやバリエーションが豊富であることが考えられます。
競合分析の際は、下記の考え方が重要になります。
- 自社の理解を深める
- 楽天ユーザーの特性を理解する
- 競合他社との違いを明確にする
- 自然検索とRPP広告の露出・流入状況を可視化する
- 顧客ニーズを理解し、RPP占有率を最適化する
分析の結果、市場や競合、自社の理解が深まるほか、戦略立案時の判断材料になる、リスク管理能力が向上するといった情報メリットを得られます。
一般的に、競合分析の際には3C分析やSWOT分析、4P分析、コホート分析が用いられます。
それぞれの分析方法にメリットやデメリットが存在するため、いずれかひとつだけの分析方法を採用するのではなく、複数を使って分析することをおすすめします。
数値面で売り上げを知りたい場合は、競合店舗の売り上げランキングやレビュー、市場調査や業界データを利用して概算しましょう。
競合店舗を知ることで自店舗の現状も知ることができるため、定期的に調査しておくことをおすすめします。